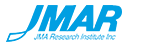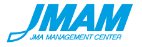グループシナジーを生む
若手リーダー交流研修 in 永平寺町 2025
禅の里で芽生えた未来への連携とウェルビーイング 2025.6.30

JMAHDは「グループシナジーの最大化を促進するための機会の創出」を掲げ、法人間の人的交流を深める取り組みを続けています。その一環として、2025年5月、福井県永平寺町にて「若手リーダー交流研修」を実施しました。
本研修の目的は、グループ各法人から選抜された若手人材(将来のリーダー候補)が互いを知り、ネットワークを築くことにあります。日常の業務や一般的な研修では得られない社会課題を五感で捉え、地域で挑戦を続けるリーダーたちとの対話を通じて、自身のキャリアや役割を深く考える機会となりました。また、グループが大切にしてきた価値観を共有し、法人の枠を越えた連携のきっかけをつくることも狙いとしています。
こうした学びを実現するため、JMAHDでは「越境学習(ラーニングワーケーション)」の手法を取り入れています。
舞台となった永平寺町
研修地となった福井県吉田郡永平寺町は、県都・福井市に隣接し、九頭竜川が中央を流れる自然豊かな町です。大本山永平寺や吉峰寺、松岡古墳群といった歴史文化資源を有すると同時に、福井大学医学部や福井県立大学などの学術研究機関も立地しています。
この地で参加者は、禅の精神に触れて自分自身と向き合い、「真の豊かさ(ウェルビーイング)」とは何かを考えました。さらに、地域づくりに挑む人々と語り合うことで、持続可能な社会を見つめる新たな視点を得ることができました。
また、2024年春の北陸新幹線延伸により「100年に一度の転換期」を迎えた福井は、多様なチャレンジが芽吹く舞台でもあります。変革のただ中に身を置く体験は、若手リーダーにとって価値観を揺さぶられる貴重な学びとなりました。
実施内容
期間:2025年5月19日(月)~23日(金)(4泊5日)
事前研修:4月23日(水)オンライン
事後研修:6月30日(月) JMAビル
参加者:グループ各法人(JMAS・JMAC・JMAR・JMAM)から若手リーダー16名
研修プログラム
● DAY1:永平寺町を知る
初日は永平寺町の魅力発信拠点「えい坊会館」でオリエンテーションを実施。町の歴史や文化について学んだ後、曹洞宗の開祖・道元禅師ゆかりの吉峰寺を訪れました。老師の講話や「葉っぱ寿司」づくりを通じて、地域の食文化や人の温かさに触れ、緊張していた参加者同士も自然と打ち解けていきました。


● DAY2:持続可能な社会を考える
2日目は、えちぜん鉄道の貸切車両で「地域交通再生」の取り組みを学びました。住民と共に築かれた“地域共生型経営”のリアルな話に、リーダーとしての使命感を刺激されました。午後は再び吉峰寺を訪問し、座禅や精進料理を体験。「五観の偈」に学び、日々の営みを見つめ直す時間となりました。


● DAY3:禅とウェルビーイング
3日目は早朝に大本山永平寺を訪れ、荘厳な朝課に参加。修行僧の読経に包まれ、自身の生き方を省みました。その後、永平寺町役場や地域団体から少子高齢化に対応するMaaSや「ご近助タクシー」の取り組みを学び、地域交通の持続可能性について議論。午後は福井県立大学・高野翔准教授による「ウェルビーイングとまちづくり」の講義で、カードワークを通じて価値観を共有し、「居場所と舞台」の重要性を実感しました。


● DAY4:幸せを感じる組織を考える
4日目は、創業100年を迎える織物メーカー・松川レピヤンを訪問。伝統を守りながら挑戦を続ける姿勢に触れ、ものづくりと働き方の関係を考えました。その後「幸せを感じる組織」をテーマにグループワークを実施し、各社の経験を持ち寄って意見交換。午後にはJMAHD役員が加わり、経営陣との対話や懇親会を通じて、グループの未来や事業連携について率直に語り合いました。


● DAY5:学びを自組織へ持ち帰る
最終日は「こっそりバディ」による相互フィードバックで5日間を振り返り。永平寺町での体験や仲間との対話から得た視点を整理し、それぞれが自組織での実践に落とし込みました。笑顔と真剣さが入り混じる場は、若手社員が未来に向けて踏み出す大きな一歩となりました。

参加者の声
永平寺での修行や地域の方々との対話を通じ、普段の業務では得られない気づきを得ました。学んだことをキャリアに活かし、横の連携にも挑戦したいです。
【参加者Aさん】
部署や年代を超えて話し合う機会は新鮮で、互いの違いから学びを得られました。こうした場が広がっていけば、さらに絆が深まると感じています。
【参加者Bさん】
立場の違いから壁を感じる場面もありましたが、懇親会では協業のアイデアが自然に生まれました。少人数で深く語り合えたからこそ、“次につながる連携”の芽を確かに感じました。
【参加者Cさん】
新たなネットワークが拓く次の可能性
今回の研修を通じて、参加者は「集団天才」の精神を体感し、組織や業種の枠を超えてつながることの価値を再確認しました。永平寺町という特別な学びの場で得た経験は、個人の成長にとどまらず、グループ全体の未来を形づくる力へとつながっています。
実際に、研修後には「新入社員研修パッケージの共創」や「手帳活用術の勉強会」など、具体的な連携アイデアも生まれています。小さな芽がやがて大きな協業へと広がっていく――JMAHDの越境学習は、その第一歩を支える場です。
今後は、日常的にグループ間交流が生まれる仕組みづくりや、経営層と若手が未来を語り合う機会をさらに整えていきます。法人の強みを掛け合わせた新しい事業やサービスを創出し、社会へ還元していくことを目指します。
JMAHDはこれからも、社員一人ひとりが主体的に学び、挑戦を続ける文化を育みます。そしてグループ全体の成長を加速させるとともに、日本から世界へ新しい価値を発信していきます。
これまでの越境学習(ラーニングワーケーション)の取り組みについては、ぜひ関連レポートをご覧ください。